2017年に出版された、健康を維持するための食事術に関する一般向けの本。
ページ数は280ページ弱で、難しい専門用語は使われていないため、非常に読みやすい。
著者の牧田善二氏は糖尿病専門医、医学博士で、糖尿病をはじめとする生活習慣病、肥満の患者20万以上を診てきた実績を持つ。
構成としては、第1章で、最新の医療データをもとに「医学的に正しい食べ方」をまとめ、第2章以降で「肥満」「老化」「病気」のメカニズムとそれらを防ぐ食事術、最後の第6章では「長生きするためのルール」について述べている。
なお、筆者も本書で述べていることだが、食と健康に関する常識は変化するものであり、ときには真逆にひっくり返ることもある。
本書の「最新」はあくまで2017年の最新であることには注意したい。
医学的に正しい食事
健康は毎日の食べ物、食べ方と密接に関係しており、特に不調の原因の9割とも言えるのが「血糖値」である。
肥満や不調、老化を抑えるために大切なことは糖質の制限及び血糖値の急激な変動を防ぐことであると、本書を通じて筆者は繰り返し主張している。
最新の医療データから導き出される食事の新常識は次の10個。
- 糖質が太る唯一の原因
- カロリーと肥満は関係ない
- 脂肪は食べても太らない
- コレステロール値は食事では1割程度しか制御できない
- プロテインやアミノ酸の不自然な大量摂取は腎臓を壊す
- 同じ量を食べるなら小分けにして回数を増やす方が太らない
- 果物は太る
- 疲れたときの甘いものは逆効果
- 発がん性が疑われるものは食べない
- 運動は食後すぐに行うのがいい
そして、筆者がおすすめする体にいい食べ物は次の10種類。
- エキストラバージンオリーブオイル(酸化していないもの)
- ナッツ
- ワイン(特に赤ワインや辛口の白ワイン)
- カカオ含有量70%以上のチョコレート
- 大豆製品
- ナチュラルチーズ(塩分は控えめのもの)
- ブルーベリー(サプリではなく生のもの)
- 挽き立ての本格ブラックコーヒー
- 天然の醸造酢
- 生もの
痩せる食事術
先に述べたとおり、肥満の原因はカロリーや脂肪ではなく、糖質である。
経口摂取した糖質は消化酵素によってブドウ糖(や果糖)に分解される。
血中のブドウ糖が増えすぎないように、膵臓から分泌されたインスリンが余ったブドウ糖をグリコーゲンに変えて肝臓や筋肉の細胞に取り込む。
しかし、取り込める量には限界があり、それを超えるとブドウ糖は中性脂肪に形を変えて脂肪細胞に取り込まれる。
これが肥満の原因である。
食事制限よりも運動をするべきだと言う認識が世間に広がりつつあるが、筆者は食事制限の方を優先すべきだと言う。
食事制限で筋肉が落ちるという説があるが、これは実は一般人には当てはまらない。
エネルギーとして使われる順番は、グリコーゲン→中性脂肪→筋肉のタンパク質である。
つまり、筋肉が分解されるのはいよいよ餓死しそうな段階、例えば山で遭難して何も食べずにいたような場合であって、普通に生きていて遭遇することはまずない。
また、筋肉を増やすことで基礎代謝を高めればダイエットにつながるというのは本当だが、その段階まで基礎代謝を高めるには相当の量のトレーニングを継続する必要があり、これも普通に生きている人にとっては困難である。
長期間に渡って無理なく続けるには運動よりも食事制限の方がハードルが低い。
糖質量の制限
具体的にどういった食事制限をすれば良いのか。
これは簡単で、毎日口に入れる糖質量を制限すれば良い。
減らすべき食べ物はごはんやパン、麺、イモ類。
もちろん、缶コーヒーやジュース、清涼飲料水、ケーキ、スナック菓子、せんべいなども糖質の塊なので避けるべきである。
その際、特に避けるのは夕食での糖質。
夜は糖質を溜め込みやすいので、避けるべきだが、どうしても食べてしまった場合には、食後すぐにウォーキング等の運動をすることによって血糖値の上昇を抑えることができる。
確実に体重を落とすのであれば、1日の糖質摂取量は60グラム以下に抑えるべき。
主な食べ物に含まれる糖質の量は本書にも乗っているし、検索で簡単に出てくる(例えばこちら)ので、参考にすると良い。
また、ひとえに糖質と言っても、その悪性度は異なる。
悪性度が高い順に並べると次のとおり。
- 缶コーヒーや清涼飲料水、ジュースなど
- 砂糖の入ったお菓子
- 果物
- 白米、白いパン、うどんなど
- 玄米や全粒粉パン、イモ類
糖質は生命維持のために不可欠な栄養素ではあるが、現代人は過剰摂取の傾向が強い。
摂取の際は悪性度が下位のものを控えめに食べるに留めるべきである。
食べ方
実は食べ方にもコツがあり、同じものを同じ量食べるとしても、体への影響は変わってくる。
気をつけたいのは次の2点。
- 食べる順番は、野菜→タンパク質→糖質
- 小分けにして食べる回数を増やす
どちらも、血糖値の急激な上昇をおさえることが目的となっている。
その他の食品
血糖値の急激な上昇を防ぐために、糖質そのもの以外で気をつけるべきことがある。
- 海藻やキノコを積極的に食べる
- 動物性と植物性のタンパク質をバランス良くとる(含有量は食と健康の総合サイト e840.netに掲載)
- 水を1日2リットル飲む
- 糖質はオリーブオイルと一緒にとる
- 辛口の白ワインを飲む
- シナモンをとる
パフォーマンスを最大化する食事術
「頭を働かせるには甘いものを食べろ」というのは実は真っ赤な嘘である。
急激に血糖値が上がり、ドーパミンやセロトニンが分泌されることで、一瞬、幸せな気分なれているだけで、実際に頭の働きが良くなっているわけではない。
むしろ、その後の血糖値の急激な低下は体のだるさや眠気、集中力の欠如につながるため、全体として見ればむしろパフォーマンスは落ちていると言える。
パフォーマンスを上げたいのであれば、血糖値は70~140の間に収め、少しでも上下させないことが大切である。
また、長期的健康のために添加物等の発がん性物質にも留意したい。
そのために気をつけるべき食べ物、食べ方は次のとおり。
- 糖質は朝食で、サラダやヨーグルトの後に食べる
- 果物は朝に少量、ジュースなどにせず、そのまま食べる
- パンは天然酵母、全粒粉のものを食べる(添加物にも注意)
- バターを摂取するならグラスフェッドバターにする
- 牛乳より豆乳を飲む
- 自分に合うヨーグルトを毎日少しずつ食べる
- 卵のコレステロールは気にしない
- ハムやベーコン、ソーセージといった加工肉は減らす
- 甘さが欲しいなら蜂蜜(ジャラハニーやマヌカハニー)を使う
- 菓子パンは避ける
- 早食いをしない
- ランチ後はすぐに20分歩く(階段の上り下りでもOK)
- 炭水化物は脂質(特にエキストラバージンオリーブオイル)と一緒に食べる
- 小腹が空いたらナッツを食べる(添加物や塩分には注意)
- 夕食は就寝の4時間以上前にする
- 夜は主食はとらない
- 塩分は控えめにする
- ワインや蒸留酒を飲む(ビールや日本酒、紹興酒は控える)
- 寝る前のスイーツをやめる
- 寝る前にハーブティーを飲む
老けない食事術
老化現象の原因として近年注目されているのが、「AGE(Advanced Glycation End Products)」である。
AGEはタンパク質や脂質がブドウ糖と結びつくことによって生成される。
体内のブドウ糖の量を抑えると同時に、体外からのAGE摂取量を減らすことが老化防止の有効な手段となる。
AGEを溜め込む原因は以下の4つ。
- 高血糖
- AGEの多い食べ物の摂取
- 紫外線
- タバコ
2については、AGE測定推進協会のHP等に主な食品のAGE量が掲載されている。
全体の傾向としては、同じ分量の食品でも、高温で調理することでAGEの量が増えている。
生で食べられるものは生で食べ、そうでないものでも揚げる・焼くよりも煮る・茹でるを優先したい。
また、酢やレモン汁はAGEを下げてくれる効果があることが知られている。
積極的に利用したい。
他にも抗酸化作用、抗AGE力を持つ物質があるので、以下に記載する。
| 物質 | 食品 |
| カルノシン | ウナギ、鶏肉、マグロ |
| ビタミンB1 | 豚肉、ウナギ、玄米、そば、大豆、レバー、鶏肉 |
| ビタミンB6 | カツオ、マグロ、サーモン、ナッツ類、肉類全般、野菜、バナナ、ニンニク |
| アントシアニン | 赤ワイン、ブルーベリー |
| イソフラボン | 豆腐、納豆、豆乳 |
| タンニン | コーヒー、紅茶 |
| カテキン | 緑茶 |
| ルチン | たまねぎ、柑橘類、そば |
| カカオポリフェノール | チョコレート |
病気にならない食事術
私たちの体に本来備わっている免疫力は様々な病気から私たちを守ってくれる。
しかし、誤った食生活により免疫力が低下すると、がんなどの病気を引き起こすことになる。
気をつけたいことを以下に羅列する。
- 不自然な物質(化学物質)を摂取しない
- よく噛んで食べる
- 多くの添加物は発がん性が証明されている(種類や用途例は一般社団法人日本食品添加物協会HP等に掲載)
- 無農薬野菜をたっぷり食べる(根菜類や甘いトマトは控えめに)
- 人工甘味料は砂糖以上に危ない
- プロテイン等の人工物は腎臓に大きな負担をかける
- 海藻を食べる
- 減塩
- 古い(酸化した)油は使用しない
- ポテチは最悪の食べ物
- 赤身のステーキを2日に1度、70グラムのペースで食べる
- 焦げたものは口にしない
- 生姜や唐辛子で体を温める
100歳まで生きる人に共通するルール
本書の最後の章では、筆者が文献を読み解いて把握した、長寿者たちの生活上の共通点がまとめられている。
- 豆類をたくさん食べる
- 野菜はたっぷり多種類食べる
- 坂道を歩く
- 生涯肉体労働
- 生きがいを持つ
- 健康チェックに余念がない
- 食べすぎない
- アルコールをたしなむ
- チョコレートを食べる
- 良い医者を選ぶ
まとめ
糖質、血糖値に焦点を合わせた1冊であった。
食物繊維や腸内細菌の項目では、先日読んだ、『できる男はすぐ腸トレ 挫折知らずの、男磨き最強トレーニング』と共通するところもあり、ある程度の説得力があると感じる。
本書はあくまでも食事術に焦点を絞ったものであるため、筆者も述べるように、かっこいい肉体美をつくりたいなど、別の目的があれば運動なども取り入れなければならないだろう。
傾向として、本書に書かれているようなことを実践するのは(少なくとも出版時点では)有意義だろうが、個人個人で実践できる範囲も異なるため、試してみて体に合うと感じたものを取り入れていくのが良いと思う。
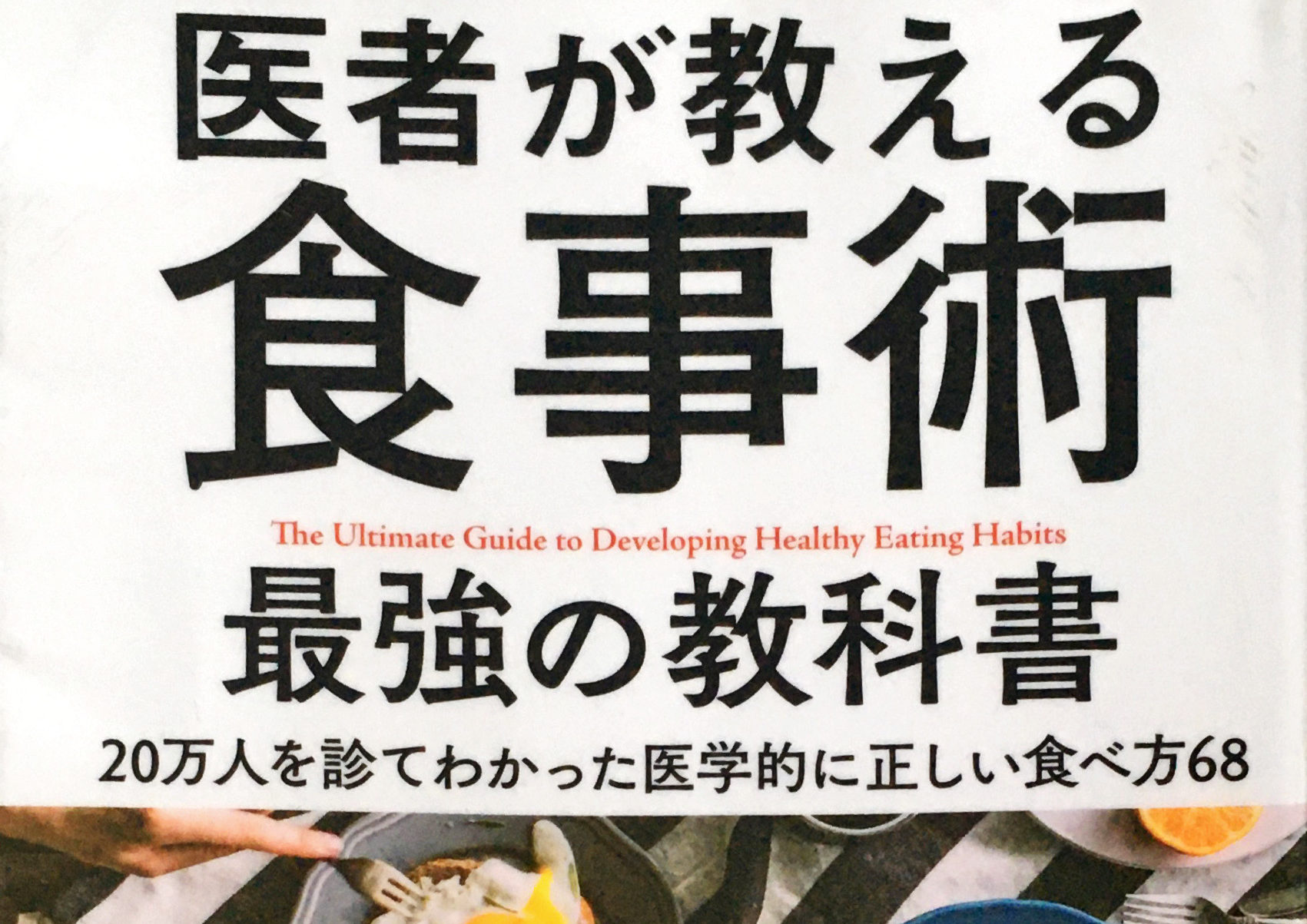




コメント